令和7年度大阪体育大学大学院・大阪体育大学入学式が4月2日(水)、大阪府泉佐野市のスターゲイトホテル関西エアポートで挙行されました。

過去最多の新入生800名が参加した入学式
入学生は、学部生がスポーツ科学部2期生598名、教育学部11期生173名の計771名(昨年比31人増)、大学院生は博士後期課程25期生4名、博士前期課程34期生25名の計29名(同7人減)。合計は、2年前から76人増えた昨年をさらに24人上回る800名です。
大阪体育大学は東京五輪翌年の1965年に西日本初の体育・スポーツ系大学として開学し、今年創設60周年を迎えました。節目の年に過去最多の新入生を迎えました。
式では、入学生1人ひとりの氏名が読み上げられた後、1日に第10代学長に就任した神﨑浩新学長が入学を許可しました。続いて神﨑学長が式辞を述べ、野田賢治・浪商学園理事長があいさつし、新入生を歓迎しました。
また、藤原敏司・熊取町長からご祝辞をいただきました。

真剣な表情の新入生
その後、入学生を代表し、大学院新入生総代の千古(せんこ)実奈代さんが「より実践的かつ科学的な視点から保健体育教育の在り方を深く研究します」、スポーツ科学部新入生総代・小松起(ゆき)さん(高知・土佐高校出身)が「諸先輩が築いた歴史と伝統を大切に、日本スポーツ界をけん引する存在になれるよう精進します」、教育学部新入生総代・布袋屋(ほてや)詩さん(大阪・泉北高校出身)が「全国から集まった仲間と切磋琢磨し、多くのことを学び成長し、社会に貢献できる人材を目指します」と宣誓しました。
最後に学歌を斉唱し、閉式しました。
式にはご家族・関係者の方も多数参加し、別室の会場でライブ中継を見守りました。
【神﨑浩学長 式辞】
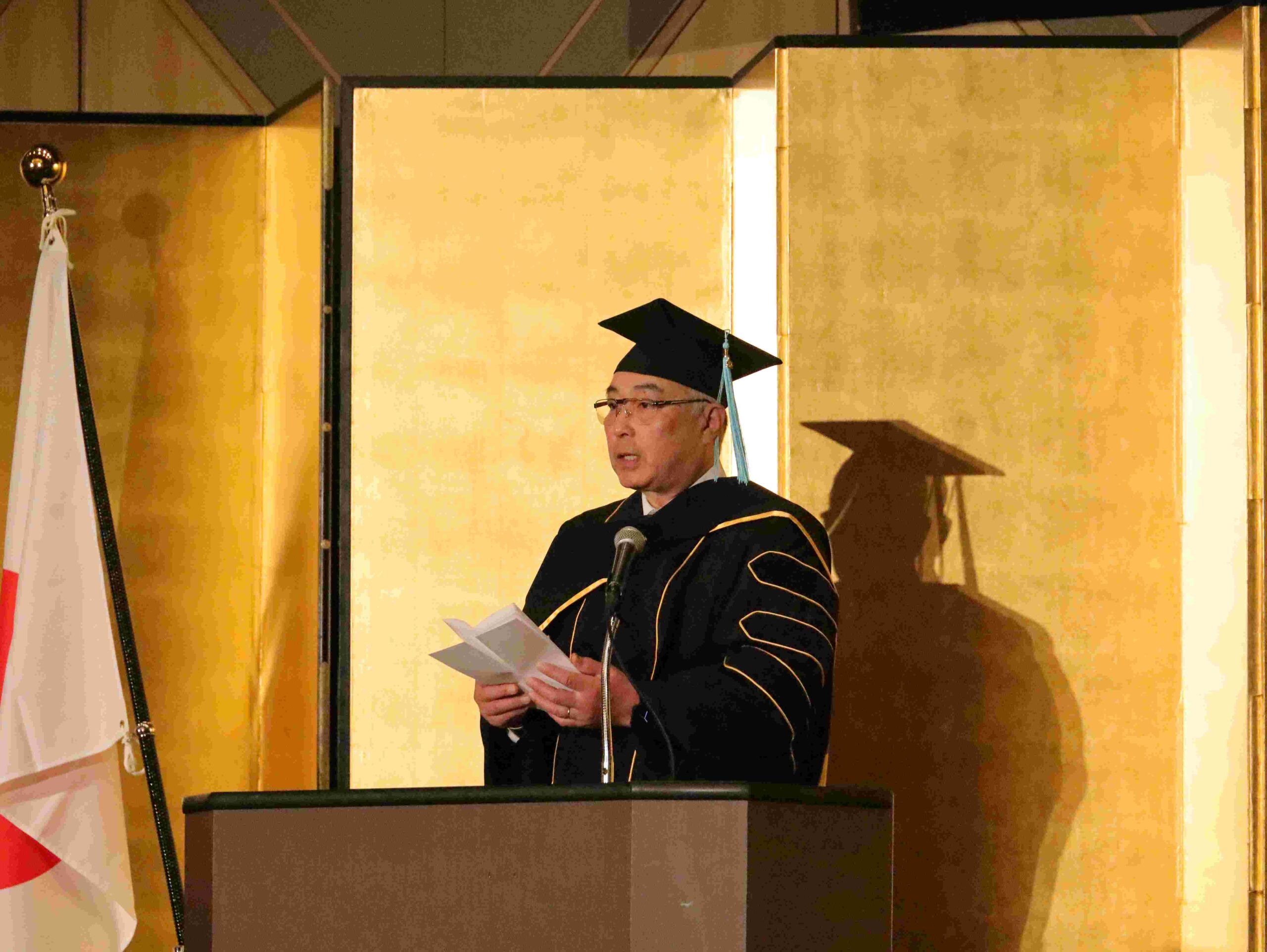
式辞を述べる第10代・神﨑浩新学長
新しい年度を迎え、春爛漫の今日の良き日に令和7年度大阪体育大学大学院並びに大阪体育大学スポーツ科学部・教育学部の入学式を挙行するにあたり、教職員を代表し、心からお祝いの言葉を述べさせていただきます。
新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。また、ご家族の皆様をはじめ、ご関係の皆様におかれましても、めでたく今日、この日を迎えられたことに心よりお慶びを申し上げます。
新入生の皆さんは、今まさに将来に向けての目標と強い期待を持ちながらも一方で不安も抱えながら本日を迎えられていることと思います。これからは大阪体育大学の一員として、今心に抱いている目標に向かって、充実した日々を送っていただきたいと期待しています。
本学は、1964年の東京オリンピックの翌年、1965年に当時オリンピックに携わった錚々たる指導者を招いて創立し、今年で60年の節目の年を迎えました。1992年には西日本の体育系大学として初めて大学院を設置し、2015年には教育学部を開設するなど、学術、スポーツ、教員養成などの分野で多くの人材を輩出してきました。卒業生は今日に至るまで各方面で素晴らしい活躍を遂げ、本学のブランド力を支えていると言っても過言ではありません。大阪体育大学は、体育・スポーツ・教育を統合的に学べる総合大学として、その価値を一層高めています。
新入生の皆さんは、この節目の年に入学されたことを誇りに思い、学びの機会を大切にしながら、在学中はもちろん、卒業後も社会の中で光り輝く存在となっていただきたいと期待しています。
大学は、皆さん自身が主体的に学び、成長を遂げる場です。我々教職員は「 学生ファースト」の理念を掲げ、学生一人一人の成長を支援し、社会で活躍する人材を輩出することを目標としています。高校の「生徒」から大学の「学生」という新たな一歩を踏み出す皆さんには、これまでとは異なる学びやスポーツ活動などの取り組みの中で、広く、深く学びを展開し、新たな自分を創造していただきたいと思います。
昨年度、本学の女子ハンドボール部が全日本学生選手権大会で11連覇という前人未到の記録を更新しました。毎年工夫を凝らしながらチーム作りをし、大会に臨んでいますが、この成功は新チーム結成後、「誰がゲームに出ても遜色のないチームを作る」という目標を掲げ、主将を置かず、他者に頼ることなく一人一人がチームとして何が必要かを考え、行動を起こすことを徹底したことにあると聞きました。まさに一人一人の主体性が花を咲かせた事例です。スポーツ活動に限らず、学業や人と人のかかわりは決して自分の思い通りにはいかず、いわゆる挫折がつきものです。何の苦労もなく今日まで来た人は皆無です。これからもまさにその体験、試練が待ち構えていることを覚悟しなければなりません。そして重要なことは、その挫折や試練を指導者や新しい仲間たちの支えの下、乗り越えてこそ、そこに成長があり、逞しく、人の気持ちが理解できる優しい人格が形成されるということです。
これからの社会は人工知能AIやDXなどの科学技術が進歩し、それらを駆使する能力だけではなく、人間の幸福に貢献できる行動や成果が求められます。本学には、他に類を見ないほどの体育・スポーツ・教育分野における専門性の高い教授陣が揃っています。オンライン授業やオンデマンド授業が進化を遂げる一方で、学校やスポーツにおける指導においては、優れた技能を持つ専門家から直接学び、体験することでしか得られないものがあります。本学では、この「人から人へのハンドメイドの教育」を大切にし、専門性の高い教員と密接にかかわる授業を展開しています。この恵まれた環境の中で、先進的な学びを深め、自らの力を極めてください。
中国の古典『礼記』には、「教学相長ず」という言葉があります。この意味は「教えることで物事の難しさを知り、学ぶことで自分の知識不足を実感する。つまり教えることと学ぶことは相補い合うものである」という教えです。相手に伝えたいことをいかにして伝えるか、自分の知識の不足をいかにして補うか、この教訓を胸に刻み、課題を克服し、自らを高める努力を怠らないでください。我々教職員もまさに同じ立場であり、ともに成長を目指します。
ご入学されました皆様のご活躍を祈念申し上げるとともに、ご家族の皆様とご関係の皆様にはご支援を賜りますことをお願い申し上げます。
結びにあたり、本日ご臨席いただましたご来賓の皆様に心より感謝を申し上げます。そして、今後ともご支援とご助言を賜りますようお願い申し上げ、式辞といたします。
本日は誠におめでとうございます。
【野田賢治理事長 あいさつ】

あいさつを述べる野田賢治理事長
新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。
ご家族の皆さん、本日は誠におめでとうございます。学園を代表して、心からお祝い申し上げます。
新入生の皆さん、皆さんが入学された大阪体育大学は、学校法人浪商学園が運営する教育機関の一つです。
浪商学園は、大正10年、西暦1921年に設立され、百年を超える歴史ある学校法人です。
その建学の精神は、「不断の努力により智・徳・体を修め社会に奉仕する」。この建学の精神を体現できる人材の育成を目指しています。
浪商学園は、大阪体育大学・大阪体育大学大学院の他に同じ熊取キャンパスに、大阪体育大学浪商中学校・高等学校、大阪府北部の茨木市に大阪体育大学浪商幼稚園、京都に近い島本町に大阪青凌中学校・高等学校という設置校があり、全部で七つの教育機関から成っています。
大阪体育大学は、第1回東京オリンピック開催の翌年、昭和40年、1965年に開学し、今年創立60周年を迎えます。
開学にあたり、東京オリンピックの選手強化対策本部長を努められ、後に日本人初のオリンピック平和賞を受賞された大島鎌吉先生を副学長として、また、東京オリンピックの国際スポーツ科学会議委員で、後に日本体育学会会長に就任された加藤橘夫先生を学部長としてお迎えをしました。
当時、体育スポーツの最先端におられたお二人の思いが、大阪体育大学の教育の源です。
60年の時を経た今も色褪せることなく、脈々と受け継がれています。
新入生の皆さん、大学生活は成長と挑戦の機会に満ちています。2025年には大阪・関西万博や世界陸上が開催され、持続可能な社会に向けて革新的なアイデアや未来社会の可能性が万博で示され、そして世界陸上でアスリートの挑戦が世界に示されます。
これらは「目標を持ち、努力すること」の大切さを教えてくれます。皆さんがこれから歩む道のりは決して平坦ではないかもしれません。
しかし、挑戦し続けることで得られる学びや経験こそが、皆さんの未来を力強く切り拓く鍵となります。新しい挑戦を恐れず、自分らしい未来を築いてください。皆さんの成長と活躍を心から願って、あいさつとさせていただきます。

入学許可で新入生は1人ずつ氏名を読み上げられ起立した

藤原敏司熊取町長からご祝辞をいただいた

大学院新入生総代として宣誓する千古実奈代さん。「より実践的かつ科学的な視点から保健体育教育の在り方を深く研究します」

スポーツ科学部新入生総代として宣誓する小松起さん。「諸先輩が築いた歴史と伝統を大切に、日本スポーツ界をけん引する存在になれるよう精進します」

教育学部新入生総代として宣誓する布袋屋詩さん。「全国から集まった仲間と切磋琢磨し、多くのことを学び成長し、社会に貢献できる人材を目指します」

別室から式のライブ中継を見守るご家族・関係者の方々

式典会場で記念撮影

入学式に引き続いて安全講習会が開かれ、本学と連携協定を結ぶ大阪府泉佐野警察署員が交通事故、禁止薬物、闇バイト、オンラインカジノについて注意喚起した




![T[active]](https://www.ouhs.jp/wp/wp-content/themes/ouhs_main/assets/img/nav_department06.jpg)
![T[person]](https://www.ouhs.jp/wp/wp-content/themes/ouhs_main/assets/img/nav_department05.jpg)

BACK
社会貢献・附置施設
BACK