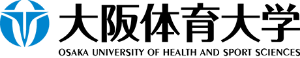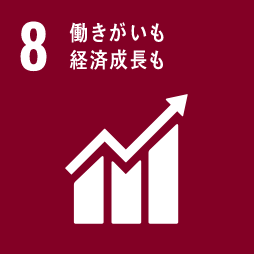大阪体育大学スポーツ科学部開設を記念したシンポジウム「スポーツサイエンスが拓く未来」(3月23日)では、ハイパフォーマンススポーツセンター(HPSC)長・国立スポーツ科学センター(JISS)所長の久木留(くきどめ)毅さん、3大会連続のオリンピック出場を決めたバスケットボール女子日本代表ヘッドコーチの恩塚亨さんが講演しました。
久木留さんは「ハイパフォーマンスからライフパフォーマンスへ」と題し、ハイパフォーマンススポーツ領域の研究の醍醐味を魅力的に語りました。恩塚さんは五輪世界最終予選でゲーム分析を徹底して日本の強みを「アジリティ・敏捷性」と定め、出場権を獲得した過程などを詳細に説明しました。
いずれもハイレベルかつ具体的な事例が満載で、スポーツ科学の魅力が詰まった講演です。
お二人の講演内容の全文を掲載します。
<基調講演>
ハイパフォーマンススポーツセンター(HPSC)長・国立スポーツ科学センター(JISS)所長、久木留毅さん
「ハイパフォーマンスからライフパフォーマンスへ」

久木留毅さん
原田宗彦学長とは国の審議会をはじめ東京オリパラ招致の前から様々な会議でご一緒させていただいている。大阪体育大学と私たちの組織は連携協定を結び、人事交流のほか大学院の授業も担当している。大阪体育大学のOB・OG多数がHPSC/JISSで働き、みなさんとはかなり近い関係だと思っている。大阪体育大学とHPSC/JISSの関係は大変深く、今後も深めていきたい。
私が一番思っているのは、ハイパフォーマンス領域で培った知見を地域のライフパフォーマンス領域、例えば、高齢者の健康や子どもたちの育成につながる取り組みを、スポーツ医・科学を通して進めていきたいと考えている。
まずは「ハイパフォーマンススポーツ」という言葉を皆さんに紹介したい。世界一を競い合うアスリートが高度で卓越したパフォーマンスを発揮するスポーツ、これを「ハイパフォーマンススポーツ」と私たちは呼んでいる。私たちの主たるフィールドであるオリンピックやパラリンピックに加え、サッカーやラグビー、また、野球の大谷選手たちがいるアメリカ4大スポーツ、これらも「ハイパフォーマンススポーツ」と呼んでいる。さらには、世界のリーグで活躍する選手も「ハイパフォーマンススポーツアスリート」だ。昨今、世の中が移り変わり、スポーツの世界でもサイエンステクノロジーを活用したものとして、例えばGPSを活用した映像分析のほか、AIを活用しビデオ分析を即時でフィードバックする方法がどんどん取り入れられている。みなさんもテレビで、ダルビッシュ選手、大谷翔平選手がトラックマンといわれるデバイスを用いて、自分の投球を終えた後どんな回転数か映像で確認している場面を見たことがあるのではないか。バスケットボールなどでも分析は欠かせない。「ハイパフォーマンススポーツ」に影響を与えるのは、サイエンステクノロジーだ。このサイエンステクノロジーを使いこなすためには、スポーツ科学の力が必要なことを理解しておいてほしい。
さて、私はナショナルチームのコーチを長くやっていたが、競技力強化の構成要素を考えてみると、一番シンプルなのは、卓越したアスリートがいないとハイパフォーマンススポーツは成り立たないという点だ。ただ、コーチの養成は絶対に必要である。もう一つ必要なのは場所。体育館、フィールドがあってもそれだけではスポーツ医・科学を活用できず、体育館の横に宿舎があり、レストランが用意されていることが必要だ。大阪体育大学のフィールドはこの「場所」の条件を満たしている。そして最後に大事なのは試合。レベルの高い試合をこなさないと強くはならない。ただ、そこを支えていくスタッフがスポーツ医・科学の様々な分野、システム、プログラムを持っていないとアスリートを育て、支えるスタッフを育てることはできない。その意味では、予算も含めて競技力強化の構成要素は、もっと複雑になる。その中でスポーツ医・科学をどう使うかを学ぶことができるのが大学だと思う。
競技力の競争構造は変化している。高速化・高度化がどんどん進んでいる。陸上競技の100mは昔と比べて記録が上がり、ウサイン・ボルトさんの世界記録9秒58を抜く選手はまだ出ていないが、おそらく抜いていくであろう。水泳、スピードスケートなどでも高速化が進む。高度化の点では、体操は1964年東京五輪でウルトラCと言われたが、今はウルトラI。6段階上がっている。ウルトラIの演技を男子の選手たちはやっている。さらに毎日毎日、最大限にトレーニングをしているため、高強度の負荷が体にかかる。高強度の負荷がかかった体を高品質のスポーツ医・科学を使った支援でリカバリーしていかなければいけない。このことを分かっていると、この試合はやめよう、この試合には出ようと選んでいくための焦点化が必要であることが理解できるだろう。
競技は進化と深化を繰り返しながら、どんどん競争構造の変化が起こっている。私が話していることも5年後、10年後には変わっていく。競技は進む「進化」と、深堀の「深化」が両方進んでいる。このことが分かっていると、「リカバリーは必要だよね」「そうしないと明日の練習で負荷をかけすぎるとけがをする」と考えるようになる。けがをしないような食事の取り方やメンタル、セラピーがなぜ必要なのか理解しておくことは重要だ。
このグラフはスピードスケートの記録だ。1998年長野五輪のスピードスケートでスラップスケートという道具が出てきた。道具によってスポーツは変わる。小平奈緒さんは2018年平昌五輪女子500mに出場し、36秒94のタイムで優勝したが、その30年前の1988年カルガリー五輪は男子の黒岩彰さんが36秒77で銅メダルを獲った。つまり、男子の記録に30年たって女子が追いついた。男子の記録は今、33秒台に入っている。どんどん進化しているのが「ハイパフォーマンススポーツ」だ。ただ、その中で重要なのは道具、マテリアルの変化で競技が変わっていることだ。
パラリンピックスポーツもハイパフォーマンス化している。パラリンピックのマルクス・レームという選手は走り幅跳びで8m72を跳ぶ。オリンピック選手のマイク・パウエルさんの世界記録は8m95。差がどんどん縮まっている。100mの記録も速くなっている。パラリンピックの記録の伸びの要因には体力もあるが義足の進化もある。マテリアルと人間が一緒になって記録を伸ばしていく。これがパラリンピック。将来的にはオリンピックの記録を抜くのではないかといわれている。こういったところにも注目すると、スポーツ科学の面白さが分かっていただけるのではないかと思う。
サッカーで、ボールを常にキープしながら相手のゴールに向かっていくことをポゼッションサッカーと言うが、今どんどん選手のボールの保持時間が下がっている。2006年のW杯で3位になったドイツが、2・8秒。2014年ブラジル大会で優勝した時は約1秒になった。これもテクノロジーが裏側で関わっている。詳細は省くが、いろいろなところから様々なものが入っていることが分かると、スポーツ科学が楽しくなってくる。
「アスリートファースト」という言葉をよく聞く。それは当然のことだが、私たちは「パフォーマンスファースト」、つまり、パフォーマンスを上げるためにどうしたらいいか。この観点でテクノロジー、スポーツ医・科学を活用し、支援と研究を行っているのが国立スポーツ科学センター(JISS)だ。東京都北区西が丘にサッカー場(味の素フィールド西が丘)、JISS、NTC(味の素ナショナルトレーニングセンター)ウエスト・イーストなどがあり、これらをハイパフォーマンススポーツセンター(HPSC)と呼んでいる。機能は様々だが、その一つは世界基準のトレーニング場を持っているということ。最先端のトレーニング場を、様々な競技をサポートするかたちで置いている。さらに、私たちは各競技団体(NF)が4年、8年先を見据え策定した強化戦略プランについてコンサルテーションという形でアドバイスしている。さらにアスリートを支えるシステムやプログラム、また皆さんが今後なるかもしれないサポートスタッフのシステムやプログラムを作ると同時に、スポーツ医・科学、情報面から支援と研究を行っている。
私はずっと、インスティテュート(研究所)という言葉にこだわってきた。私たちは支援と研究でアスリートを支えている。ハイパフォーマンス領域の研究を支援に返し、支援での様々な課題を研究に返すべきだと考えている。その中でJISSが行っているサポートの特徴はトレーニングの可視化だ。リアルタイムでモニタリングして、実際に即時確認をし、修正して現場に戻している。この大阪体育大学にもあるような施設を介して様々なことを行っているが、特に私たちは標高5000mに調整できる低酸素トレーニング室を有している。低酸素宿泊施設も備えている。風洞実験棟やハイパフォーマンスジム、様々なコンディショニングを行え、講義やコミュニケーションできるスペースも備えている。こちらの映像は、風洞実験棟だが、可視化が可能で、選手の目の前にモニターがあり、自分がどれぐらい風を受けているのか瞬時に見ることができる。スキーのジャンプ競技で、腕をどれぐらい広げたらいいのか、前傾姿勢をどれぐらい保てばいいのか、ここで試行錯誤している。ちなみにジャンプ競技は滑って飛ぶ。その間は助走が約5秒、ジャンプが約5秒で合計約10秒。本当のジャンプ台では1日にだいたい5本から6本しか飛べないそうだ。しかし、この風洞実験棟に20分間いるだけで3か月分のトレーニングができるといわれている。例えばラージヒルという100mを超える地点から滑る風を、小学生や中学生も体験することができる。これがHPSCの風洞実験棟の強みだ。JISSでは測定しながらトレーニングできることが一番の強みである。
さらに平昌五輪で金メダルを取ったスピードスケートのパシュートという競技を様々な形でサポートした。3列縦隊の前と後ろの選手などのデータを取ることによって戦術立案への情報提供をしている。データに基づく戦術やトレーニング、様々なものが今は必要な時代だ。だからこそスポーツ科学を学ぶことは非常に有益であり、そこから得るものは多い。
現場には様々な課題がある。激しい運動をして疲れる、疲労が抜けない、種目によっては減量に伴う精神的なストレスを感じ、女性は月経異常を起こすこともある。暑熱や寒冷地の環境、さらには長距離移動なども課題だ。私たちは、様々な課題を抽出してコンディショニングプログラムとしてまとめ、課題解決のアドバイスをコーチたちと進めている。その中で、私たちの特徴の一つとして、暑熱順化がある。暑さに慣れるため事前に順化トレーニングをしているが、温度と湿度を変えることができる環境制御室に入って暑熱順化をすると、暑さの中でも実際に疲れにくい。また、シャーベット状のアイススラリーを飲み、手のひらの静脈と動脈がつながる部分を冷やして体の温度を下げる。東京オリンピック・パラリンピックでも実施された。
東京2020大会はCOVID-19による様々な精神的ストレスや感染症対策のため、日常とは違う状態だった。生理・生化学のスタッフがサポートし、唾液に含まれるSIgAを使って体の状態を測り、「今疲れていますよ」「こういう状態ですよ」と選手にアドバイスしていた。
そういった活動をHPSCが学術雑誌としてまとめたJournal of High Performance Sport(JHPS)はハイパフォーマンススポーツ研究、つまり、「世界一を競い合うレベルのアスリートが発揮する卓越したパフォーマンスに関する研究」を対象とし、HPSCのウェブサイトで無料で閲覧いただける。ぜひ高校生・大学生・大学院生にも見てほしい。東京大会で行った様々なサポートの実態を、現場の声も含めて科学的にまとめてこの中に入れている。さらに最先端の研究もこの中にある。ただし、一般のジャーナルと違って、被検者は1人か2人等。トップレベルのアスリートを対象にしたサポートについての雑誌なので、他の雑誌と差別化をすることができる。
また、私たちは「ラボ研究から実践研究へ」ということで、論文を書くことを推奨している。実際にラボで培った知見を実践研究とし、ヨーロッパやアメリカ等のジャーナルに投稿する。このことは今までできていなかったので、推奨している。一般の海外の雑誌や、先ほど紹介した雑誌にこの知見を出している。私たちの特徴は論文にするだけではなくて、ガイドラインのようなものにまとめて読みやすくし、実際に選手の手元に届けている。これは多数の競技団体で使ってもらっている。さらに競技団体と協議して支援の結果を論文にしており、現場から同意が得られた段階で論文化し、海外の雑誌に投稿している。
合わせて、JISSは2001年10月の開所から20年以上経つが、これまでの知見を「フィットネスチェックハンドブック」という1冊の本にまとめた。氏名が特定されないかたちで各競技の体力測定等のデータが入っており、スポーツ科学に携わる方には手に取っていただきたい。
今、私たちがパリ大会に向けて考えていることの一つは、「トータルコンディショニング」。1人のアスリートに対して様々な専門家が様々なサポートをしていく時に、トータルで考えていく。例えば女子バスケットボールに必要なコンディショニングは何か、現場と話をしながら聞いていく。男女レスリング、男女柔道、サッカーなどの人たちと話をして何が競技にとって必要なコンディショニングなのかを聞く。必要なものが競技によって違う。ある競技ではトレーニングと栄養が必要だが、ある競技では睡眠が一番大事。ならば、睡眠に対するアドバイスをどうするのかなどトータルで考えていく。一番大事なのは、真ん中にいるアスリートのリテラシー、知識を上げることだ。理想はコーチのいらないアスリートを育成することだ。いろいろな判断を選手自身ができれば、「今はこのような状態だ」などと理解できる。これはいろいろなところに転換できる。
最後にまとめに入るが、私は10年先を見据えた取り組みが必要だと考えている。今、オリンピック、パラリンピックは2032年ブリスベン大会まで決まっている。2034年のアジア競技大会はサウジアラビアの首都リヤドでの開催が決まっている。10年後まで大会が決まっている時代だが、サイエンステクノロジーの分野は日進月歩である。これからはChatGPTを含めた生成AIが出てくる。10年先をスポーツという限られた中だけで見ていてはだめで、様々な分野の人たちとコラボレーションしながら情報を入れて、一方で自分達が中心となる考え方を持っていないと他分野の人たちとのディスカッションは弾まない。そういった意味で、スポーツ科学を中心に置くべきだと考えている。
私たちHPSCは、10年先を見据えて実際にASEANを中心にヨーロッパ諸国も含めて2国間連携を8カ国12組織、複数国間を16カ国21組織と結び、昨年11月には世界ボート連盟と連携協定を結んだ。私たちは国境がなくてボーダレスな中で世界一を競うアスリートを支えている。いろいろなところと競争はするが、情報の共有、人事交流、共同研究を進めていく。また、私たちは独立行政法人、ナショナルエージェンシーであり、各国の様々なトレセン連合、オリンピック・パラリンピック委員会と連携協定を結んでいる。そこが私たちと大学との大きな違いだ。ただし私たちは大阪体育大学と連携協定を結んでおり、大阪体育大学が私たちとの連携協定を介して、スポーツシンガポール、AIS(オーストラリア国立スポーツ研究所)などと連携することは十分可能だ。
さらにハイパフォーマンス領域で培った栄養、心理、映像、体力測定など様々な分野をパッケージ化して、研修プログラムとしてHPSCが承認したものを地域に展開している。これらを大阪体育大学で使っていただくこともできるし、大阪体育大学から和歌山、大阪、京都、滋賀など様々なところへ展開していくことも十分できる。こういったことを考えて仕事を進めている。ハイパフォーマンス領域で培ったものを大学、中学校、小学校などに展開する。そのために大学との連携は欠かせない。私たちはハイパフォーマンス領域には専門家として関わっているが、実は小学生の体力や高齢者の体力に関する専門家はない。もし大阪体育大学にその専門家がいれば、私たちが培った知見のトランスレーターになってもらい、新たなパッケージを作ることは十分に可能だと思う。
私たちは15の大学・機関と連携協定を結んでいるが、HPSCの知見を地域に展開していく時に、特に関西で展開するためには大阪体育大学との連携は重要である。実践できる科学者、実践できるスポーツ医・科学の専門の方と一緒に取り組んでいきたいと思っている。冒頭で話したようにこの大学からたくさんのスタッフが私たちHPSC/JISSに来ている。こういった連携を考えながら、「ハイパフォーマンススポーツ」とはどういうものか、皆さん方にその一端をお話した。私たちがやっているスポーツ医・科学とはどういうものか、地域への展開をどう考えているのかをお話して、私の話を終わりにしたい。
<記念講演>
バスケットボール女子日本代表ヘッドコーチ、恩塚亨さん
「バスケットボールコーチの視点から」

恩塚亨さん
私と大阪体育大学の関係は、前職で大学(東京医療保健大学)のコーチをしていて、2012年、初めてインカレに出場し、初戦で大阪体育大学に当たった。57―87でボコボコに負けたところから大学のコーチをスタートした。
私はスポーツサイエンスがなかったら、この場に立っていない。選手としての実績もない。今日ここ(大阪体育大学)に来る途中に車内で後輩と話していると、後輩から「(私が)代表監督になるなんて思っていなかった。他のバスケットボール部の仲間もそう思っている」と言われた。
私が人生で一度は日の丸を付け、バスケット界に恩返しするために何かできることはないか、実績のない私が始められることはないかと考え、始めたのがスポーツ科学。今日のテーマで言うゲーム分析だ。私はゲーム分析を掘り下げることでコーチングができるようになったし、大学でインカレ5連覇を果たして代表コーチになり、2月の五輪予選で勝つことができた。もし私がこれをやっていなかったら、私はここにいないと本当に思っている。これから未来を拓こうと思っている皆さんに、私の経験が少しでも役に立ってほしいと思っている。
そもそもデータ哲学、データを扱うときの心構えは、「勝つべくして勝ちたい」ということだ。「一生懸命」「思い切ってやる」は、スポーツの最後の最後でかける言葉だが、そこに至るまでは「勝つべくして勝つ」準備が必要で、そのためにはデータが不可欠だ。データと言うと、情報が多くて取り扱いが難しそうだが、行き着くところは、自分たちの行動に移せるかどうか。「これをやったら勝てるよね」に行き着く情報でないと価値はない。いろいろなデータを扱ったとしても、「こうやったら勝てる」という論理的確信につながるデータを使えるようにしたい。
今日は、私がどうやってバスケットボールを分析し、論理的な確信に至ったのかというプロセスを紹介したい。
勝負事なので絶対はないが、論理的には「絶対にこれだったら勝てる」というところまでは、スポーツサイエンスを通して持てることができる。それを持って勝負していれば、どこでつまずいたのかが分かるし、調整が失敗に終わったとしても、自分を卑下する必要はない。「これができなかった」ときちんと受け止めて、次につなげていける。きちんとデータ分析をし、論理的確信をもって臨むというプロセスを大事にしてほしい。
ではどんなデータを重視するのか。行動する目的は勝つためであり、とにかく勝つ可能性を高めるデータは何かに着目する。データにいかに優先順位をつけて本質に迫れるか、コーチのセンスが問われる。ここも「こうやったら勝てる」につながらないと意味がない。優先順位を付けやすい。
データを選ぶ2つの視点として大事にしているのは、まずバスケットボール競技の特性にしっかり向き合い、「このデータは勝ち負けに左右するよね」というポイントをつかむ。もう一つは戦略のデータ。自分たちが勝つために強みを最大化するためのコツとかポイントをちゃんと評価して、そのパフォーマンスを振り返るようにする。この二つを私は考えている。
この二つをこれから振り返りたい。
そもそもバスケットボールは、相手より多く得点した方が勝利するゲームだ。ここをつかむと、何を掘り下げるべきかが分かる。次は得点がカギになる。得点は、得点効率と攻撃回数の掛け合わせで決まる。攻撃の質と量がシンプルに関わる。得点効率の高いシュートを数多く打ったチームが勝つ確率が高いスポーツだ。これをちゃんと押さえられるどうかかが勝負に勝つためのポイントだ。なぜこんな話をするのかというと、代表チームの試合でも「何でそんなタイミングで期待値の低いシュートを打つのか」という場面がある。それは「頑張らなきゃいけない」「やらなきゃいけない」という気持ちで、期待値の高いシュートよりも「頑張る」という精神を重視するからだ。そういうエラーをちゃんと整備して「勝つべくして勝つ」ために選ぶこと、強い心構えを持つためにもこういう考え方は必要だと思う。
得点効率の高いシュートを数多く打つというデータは、効果的なシュートを打っている割合、フリースローシュートを打てている割合、シュートを打てずにオフェンスが終わる場合、リバウンドの獲得割合。この4つがバスケットボールの重要な数値ではかれる4ファクターと呼ばれる。こういう視点で、スポーツの勝負が決まるカギとなる重要なデータが何なのかをつかんだうえで、そこから目星をつけていくのが大事ではないか。データはいくらでも出せるが、これ以上大事なデータはない。バスケットは4ファクターだが、バスケット以外の人も何がキーファクターなのかをつかんで、そこで自分たちが勝負できているか、違うところで頑張っても勝てない。そこに対して厳しさを持って向き合うことが、「勝つべくして勝つ」ことにつながる。
以上が1つ目のバスケットの特性の話だが、2つ目は、戦略として勝つために、自分たちの強みを理解し、強みを相手にぶつけることが、バスケットボールなど対人競技では大事なポイントになる。自分たちの卓越性をどう見つけていくかがポイントで、自分たちの強みを分かっているかどうかは本当に大事だ。トップアスリートで結果を出している人は、ちゃんと理解している。これを分からずに「とにかく頑張る」「言われたことをやります」と言う人は、人との勝負ができず、本当の力を出せていないのではないか。
私たちは考え抜いたうえで、「アジリティ・敏捷性」が日本の女子バスケットが世界で戦ううえでのカギになると考えた。バスケットは行ったり来たりして目まぐるしく状況が変化するスポーツで、その中で素早く合理的な行動ができるということはパフォーマンスに大きく影響し、日本人はそれができる。そのため、これが一番の強みで相手に最大限ぶつけていく戦い方をしようと設定した。これもデータの活用だが、選手に動画を見せ、F1のような動きはできないが、ラリーカーのような感じで戦えば、勝ち筋を取って行ける。これは自分たちの強みで、こういうエネルギーで戦うことを強調している。また、アジリティといっても選手に響かないので、今は「走り勝つ」とコンセプトを掲げながら自分たちの強みをぶつけている。選手がイメージできる言葉になるまで情報を磨いていくと、パフォーマンスが上がっていくと思う。
また、1試合の中で何%速攻を出せたのか数値を出しながら、自分たちが走れているかどうかをチェックしている。チェックしながら目標を20%にして5回に1回は速攻をする目標を設定している。そのうえでフィールドゴールは60%をめざしているが、目標値を決めながらパフォーマンスを見て、ビデオを見ながらずれをみつけていく作業を永遠とやっている。その中で自分たちが走り切れていない、または走る中で起きたエラーなどの課題を見つけて、自分たちがぐらつくポイントを押さえて、ちゃんと走る。その繰り返しだ。
シンプルに、攻防が変わった瞬間の走り出しや1プレーごとに正しいポジションに移動できているか、こういったところをコーチらとともに、練習、試合で戦略通りに戦えているかチェックしている。選手時代に実績のないコーチが代表選手を教える時、聞いてもらえるかどうか心配になるが、「チームとしてこういうことをやりたいよね」と言うことはできる。サッカーのモウリーニョ監督の私の好きな言葉で、「メッシにドリブルを教えることはできないけれど、チームとして戦うことを教えることはできる」という言葉がある。まさに、チームとしてこう戦うんだということを、スポーツサイエンスを使って提示できたら、どんなことでもコーチをすることができる。
ゲーム分析をして課題が見つかった時に、それが個人にひもづく問題なのか、チームにひもづく問題なのかをしっかり分析するようにしている。個人の問題なら個人に対して提案するし、チームとしてやり方を改める必要があれば改める。この繰り返しだ。
分析のフローをまとめると、4ファクターを評価し、戦略で自分たちの強みをぶつけられているかどうかの評価をし、基準値をもとに分析してチェックする。それが個人、戦術のどちらにひもづくかを見極めて、優先順位の高さを決定する。こういうことを試合中も試合後もひたすら繰り返している。試合が終わって1、2時間したらデータがまとまっていて、それを見返すようにしている。
ミーティングでの事例を一つ紹介する。試合後にソフトを使って日本と中国の攻撃の映像などをチェックすると、体が小さいからリバウンドを取れないのではなく、努力不足であることが分かる。実際に一つの大会で個人としての努力不足が16回、チームとしての努力不足が13回あり、取られたリバウンドの50%以上は、努力不足が原因だった。チームで課題に感じるところは一見、弱みや分が悪い点だと思いがちだが、大体はちゃんとやるべきことをやっていないから、できていないことが多い。仕方ないではなくちゃんと科学して、自分たちのどこに問題があったのかに真摯に向き合うと、道はあるよ、勝つチャンスはあるよということをお伝えしたい。
ここまでがゲーム分析の一つの例だが、ここからはゲーム分析の情報をどう活かすか実践の話をしたい。ゲーム分析で得た情報を基にして、いかにチームとして攻撃的に戦っていくか、戦い方の科学の話だ。データは行動決定に活かすためのツールだが、行動してパフォーマンスアップにつながっているかどうかがカギになる。データはあるけれど活かせなかったら意味はない。心がけることは、自分たちが情報を得て打つ打ち手が効果的であること。連続的でチームプレーになるような打ち手になるように心がけている。情報を点の情報ではなくストーリーとして伝える。「こうやったらこうなる」と情報を因果関係でつなぐ。「こうやってこうしたら、これができるようになり、さらにこんないいこともある」という好循環がストーリーとして生まれる。ちゃんと自分たちが理解することができたら、行動しやすくなるというのが私の考えだ。データに裏付けされたストーリーを競争優位の論理で作っていきたい。このように情報を点ではなくストーリーにして提供できる人が一流のコーチだと思う。スポーツを科学することの意義や価値になる。
これをどう作るのかというと、私は台本にする。「こうやって、こうなったら、こうなる」をストーリーにして台本にする。台本はスクリプトというが、「こういうことをしたいよね」という全体像をもとに、誰がいつ何をしたらどういうことができるのかを明確にする。個人としてもチームとしても、どうプレーするのかが明確になり、選手も台本を持っていることによって、チームとして戦う術が分かりやすくなる。これを「チームワーク」などの掛け声でやっていても、まとまらないのではないかと考えている。チーム力を重視する私たち日本代表にとっては、すごく大事な戦い方だ。
バスケットでは、同じビジョンでプレーしようなどと言われるが、どうやったら同じになるのかを掘り下げて考えられるかどうかが、カギじゃないかと思う。戦い方を台本に集約する。迷わずプレーするとか、ミスを起こしそうなところを解決するシステムとか、ミスしそうなところを、こういうことを意識したらミスせずにスキルを発揮できるという考え方とか。あるいはチームとして戦う中でも個人としての強みをいかに発揮するかとか。これらを台本としてみんなが共有することができたら、一つの目標に向かって、チームとして歩んでいきやすくなる。強力で継続性がある台本ができると、「これをやったら、次はこうなるよね」ということが本人も想像できるし、周りの人もイメージできるので、プレーが速くなる。あうんの呼吸ができてくる。5人が常に同じページをイメージして戦っていける。そういう相乗効果も期待できる。
もうちょっと分かりやすく説明する。「目的から逆算する台本」ということで、例えば熊取駅から大阪体育大学まで行くとする。その時にスクリプトとして「原則バスです」と決めていたら、駅に着いた時、「(移動手段をバスにするかタクシーにするか)どうしよう」といちいち考えずにそのままバス停に行き、移動できる。周りの景色を楽しんだりもできる。心の余裕も持てるし、いちいち考える必要もなく、立ち止まらなくてもいい。ただし、台本では「原則として」がポイントだ。もし、バスがすでに発車していたら、時間がなければタクシーを使うかも知れない。こういうところまで整理しておくと、原則通りに何もなかったらさっと行くという規律ができ、トラブルが起こった時やまたはもっといいチャンスがあった時にアドリブを利かせられるようになる。こういう現在地と目的地を決めながら、「原則こうしようよ」と決めつつ、もっといいことがあったら「アドリブを使っていいよ」と設定できると、自分たちが同じケージで規律と即興を持ちながら戦える。
今までは、こういう部分は「スピード」「速く」「頑張れ」など大きな言葉で選手に伝え、選手が大きな言葉を選手なりに解釈してそれができるようになることをめざすのが、これまでよく行われてきたコーチングだ。「スピード」という大きな言葉だけではなくて、ちゃんとチームとしてこう戦うんだという絵や台本を持たせることが重要。それがなかったら、出たとこ勝負になったり「とにかく頑張る」と乱戦になったりして、非効率になる。
皆さんはスポーツに人生をかけるつもりで大学に来られたと思っているが、私は、自分の人生ではギャンブルは嫌で、勝つべくして勝ちたい。自分が納得する勝負をしたい。そのためには、どういうところでつまずくのか、どうやったら勝てるのかをちゃんと科学して向き合うことが大事だし、それがあったおかげで今ここにいると思っている。
まとめていくと、論理的確信に向かってゲーム分析を積み重ね、台本を作る。台本を作った後はそのスクリプトをリハーサルする。それが練習だ。ここでは、丸暗記するのがポイントだ。丸暗記してできるようになって初めて試合に臨む。このプロセスをちゃんと踏んでできるかどうかがパフォーマンスのカギだと思う。
これができることによって、ごちゃごちゃした乱戦を避けて、勝つべくして勝つ戦いに向かえる土台になる。代表選手に「プレーの丸暗記ってどうですか」と聞いたら、「ロボットみたいに頭が固くなる気がする」と言われた。その気持ちは分かるが、私が絶対丸暗記しなければだめだと思えるようになったエピソードを紹介する。
私の友人で世界のトップバンカーの話だが、優秀な営業マンは営業トークを完ぺきに丸暗記しているという。丸暗記していないと、お客さんに対しながらその時々でどう話そうかと考えてしまう。商品の良さをどう伝えようか考える。その時は、お客さんが買う方向に振れているのか振れていないのかを読むことができないという。丸暗記していると、話す内容を考えずに、相手の反応だけ見るらしい。相手の反応を見ながら、持っている自分の技や営業トークを出すという。これってスポーツと同じだ。次に何をしようかと考えながら、目の前のディフェンスがどういう状態にあるのか読めるだろうか。相当難しいと思う。自分たちの戦うスクリプトをちゃんと頭に入れて置いて、それをベースにしながら、目の前のディフェンスが自分をどう妨害してくるのだろうと意識を集中させるから、ディフェンスに対して効果的な打ち手を正確に選べる。これが私の考えで、「勝つべくして勝つ」に近づくカギだと思っている。
結局、マインドを実行するのは人間で、分かっていたからできるものではない。今から映像を1秒間だけ見せるので、赤が何個あるか数えてください。(映像終了後)7個でしたね。では、青は何個でしたか。
人間は1秒間に五感を使って2000個ぐらい感知できるが、実際に自覚できるのは8個ぐらいだと言われている。脳は重要なこと以外は省略する。重要かそうでないかは、自分が決める。今回は「赤を見よう」と思った時に重要なことを決めた。「自分がやってやる」とか、自信がある時は、ドリブルして進める、空いているコースが見える。自信がなくなるとそのコースは見えなくなる。なぜかというとパスをしたいからだ。パスをする所が赤になる。自信がある時の赤は、目の前の線になる。そういう意味でスクリプトをひたすら覚え込んでトレーニングしたからといって、試合で(効果が)出るわけではない。自分の心を整えながら、「私ならできる」と思っている人だったら、「私ならできる」が「やっぱりできる」になる。「できる」と思ったら、できることが見えてくる。できそうな、行けそうな道が見えてくる。「私、だめだ」と思ったら、やっぱりできないという世界が見えてくる。それが人間だ。なので、スクリプトを大事にしながらも、人としての心をちゃんと持って、規律ばかり言うのではなく、「やってやろう」という気持ちを持てるようにコーチは選手を導くし、選手自身も「私ならできる」という気持ちでスクリプトに向き合うことが情報を活かすカギになる。
データは行動に活かすためのツールであり、知性をもとに勝つべくして勝つ。論理的確信に向かってデータを集約してスクリプトにし、やりたい気持ちでプレーできるように導くことが、私がめざしているコーチングだ。こういうチャレンジを通してパリオリンピックで金メダルを取って帰ってきたい。