1月22日(月)、本学中央棟にて大体大DASHプロジェクトセミナー「オリンピックとスポーツ医・科学」が本学の教職員、大学院生に向けて開催されました。
講師として登壇したのは前国立スポーツ科学センター・センター長の川原 貴 氏。現在は日本臨床スポーツ医学会理事長を務める他、日本版NCAA設立に向けた学産官連携協議会安心安全ワーキンググループのメンバーの1人としてスポーツ医科学の観点から日本のスポーツの振興に尽力しています。
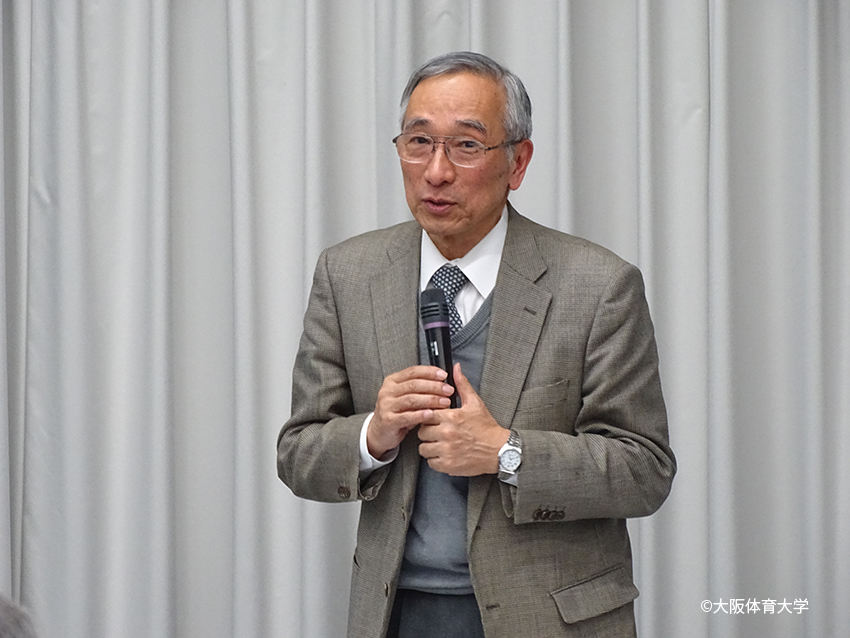
川原 貴 氏
冒頭、川原氏はこれまでの日本のアスリートサポートの歴史について説明しました。
日本における本格的な医科学によるアスリートサポートは1964年の東京オリンピックから始まり、1960年に東京五輪選手強化本部が設置され、掲げた目標は金メダル獲得数世界3位。当時の日本は、指導者の養成、医科学の導入、トレーニング拠点の確保の3つの柱で選手強化に取り組み、結果は金メダルを16個獲得し世界3位の目標を達成しました。
しかし、東京五輪後は選手強化、医科学サポートシステムが残らず、日本体育協会が実施してきた研究プロジェクトも縮小されました。その結果、育成システムや選手サポート制度を充実させた他国の後塵を拝すことになりますが、2001年に国立スポーツ科学センターが設立されアスリートをサポートする環境面が整備されてきました。
川原氏は「これまでの日本の問題は金メダルを取れるのが競泳、レスリング、柔道、体操の4種目にほぼ限定されていたこと。それが最近ではこの4種目以外にも金メダルを取れる種目が出てきた。これは選手をサポートする環境面が整備されてきた成果が出ているのではないかと思います。2020年東京オリンピックに向けて、日本オリンピック委員会は『金メダル数世界3位を目指す』、スポーツ庁は『過去最大のメダル数を』と言っています。オリンピックで勝つためには才能のある選手と優秀なコーチは勿論必要ですが、最近はそれだけでは勝てなくなっている。マネジメントや情報収集するためのスタッフ、ドクターやトレーナー等の医学的なケアも必要になります」と、これからの日本のアスリートサポートにおいて、これまで以上に多方面からのサポートが必要不可欠であるとの考えを示しました。

当日の様子
また川原氏は、アスリートのハイパフォーマンスサポートに関する問題点として「人材の問題」と「研究とサポートのバランスの問題」の2点を挙げました。
人材の問題については「アスリートをサポートする人材は多数いるが、継続的な契約形態の人材は3割しかいない。一方で7割が期限付きの契約であるため、せっかくスペシャリストになった人材が期限満了で継続できない。そういった人達の力をジュニア世代の育成や強化指定選手が地域を拠点に活動する際などに活用できないか」との提案を投げかけました。
研究とサポートのバランスの問題については「研究機関としてはアスリートをサポートする中で得たデータが研究につながっていけば非常に良い形で進んで行くと考えられる。しかし、実際に現場でサポートをしていると体力測定や競技の撮影や記録などがルーティーン化し、研究者の技量をあまり生かせないということがある。そこのバランスをどうするか」と研究やサポートの現場が抱える課題についても言及しました。
講演後の質疑応答では、本学の土屋裕睦教授から「JISSに関しては本学でもインターンシップなどで学生がお世話になっています。本学を卒業した学生がJISSの研究員として勤めた後、また本学に戻って来てくれたり、他大学等で教鞭を執ったり等が実現すると、国内の研究レベルの向上や研究者人材の交流にとっても良いことだと思うのですが、そのような方策を検討するなど可能性はありますでしょうか?」という質問に対し、「仕組みとしては受け入れられるようになっています。研究プロジェクトの一部を担ってくれるのであればJISSの施設の使用も可能。交通費や住居等に関しては自己負担になりますが、そこがクリアできれば受け入れは可能です」と新たな交流における可能性が示唆されました。

質疑応答で質問を投げかける本学土屋教授
また、本学・貴嶋講師からは「以前はトップアスリートのデータが少なかったため、まずはデータを収集するということが目的のようなところもあったかと思います。現在では膨大な数の日本のトップアスリートのフィットネステストデータがJISSには蓄積されているかと思われますが、それらのデータの解釈をどのように捉えているのか。その解釈が示されているのであれば、例えばJISSにあるトップアスリートのデータと本学の学生アスリートのデータを比較することなどが可能であれば、指導現場でデータをもとにした指導として活用できる可能性があるのではないか」という質問が投げかけられました。
これに対し川原氏は、自身がJISSの元センター長であるため断言はできない立場にあることを示したうえで「そのような取り組みは必要。科学的なデータは本当のトップアスリートよりも、実はその下のレベルのアスリート育成に活きると思う。例えば各競技団体はジュニアの育成にトップのデータを活用し、このデータ活用に大学が協力をするというようなことができれば良い。だが実際には、競技団体はトップのフィットネスデータを持ってはいるが、フィットネスデータの変化と技術・パフォーマンスの変化を紐付けた分析などがなかなかできておらず、競技団体がこの必要性を理解し、必要に応じて研究機関がサポートできれば良いが、研究機関側から押し付けができないとうのが現実。そこで、大学がデータを活用して選手がどのようなトレーニングをすればパフォーマンスが上がるのかといった検証してくれれば、JISSとしても参考になると思う」と大学が持つ可能性を述べました。
講演と質疑応答の中での議論を通じ、研究専門機関との連携の中における大学が果たせる役割についても期待の膨らむ機会となりました。